白岡キーワード百科「な」
ナイフ形石器(ないふがたどき)
今から約20,000年ほど前の旧石器時代の人々が使った石器の1つである。黒曜石 (こくようせき)やチャートなどのガラス質の石を打ち欠いて得られた石片に、鹿の角などを押し当てて細かい調整加工を施している。柄を付け、他の石片数個と組み合わせて槍として用いられたと考えられている。
市内では、入耕地(いりごうち)遺跡(白岡地内)、タタラ山遺跡(白岡地内)、山遺跡(白岡地内)などから出土している。

入耕地遺跡(白岡地内)出土
梨(なし)
当市は、県内有数の埼玉梨の主産地であり、4月中旬には市内の梨園が梨の花で白一色となる。
歴史(れきし)
当市の梨栽培の歴史は、明治36年に栢間村柴山枝郷(現久喜市菖蒲町)の木村家から親戚筋の荒井新田の加藤家、同43年に上野田の小島家に伝えられたのが始まりである。その後、親戚筋を中心に伝授され、昭和初期の世界恐慌を契機に、養蚕から梨栽培に移行する農家も多かった。その後も多くの関係者の努力により、県内有数の梨生産地となった。
品種(ひんしゅ)
現在生産されている品種は「幸水」「豊水」などが中心である。幸水は当市で多く生産されている品種で、果汁が多く、 甘くて柔らかな歯応えが特徴である。豊水も生産量が多く、甘みに酸味がプラスされたさわやかな味が特徴である。当市ではこの2種類で全体の生産量の大半を占めている。
梨の収穫は8月上旬の幸水から始まり、収穫された梨は共同選果場で選果されて市場に出荷される。選果場では直売もしている。9月になると豊水の収穫の最盛期を迎える。
花かけ・交配(はなかけ・こうはい)
梨の交配は人工授粉で行われている。以前には蝶や虫によって、自花授粉で行われていたのが、消毒作業が盛んになり、蝶などが少なくなったためである。
人工受粉はあらかじめ他品種の花粉をとっておき、綿棒などの道具で花粉を人工的に授粉させるものである。梨の花が咲くと農家では家族総出で、また親戚や知り合いに頼んで行われる。
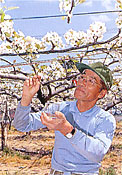
五十嵐八五郎はこちら
梨選果センター
地域農業基盤確立農業構造改善事業として平成9年、荒井新田に完成した白岡市特産の梨の選果処理施設。エリア方式選別、カラー測定、面積測定などに新鋭機器が活躍している。




更新日:2023年01月31日